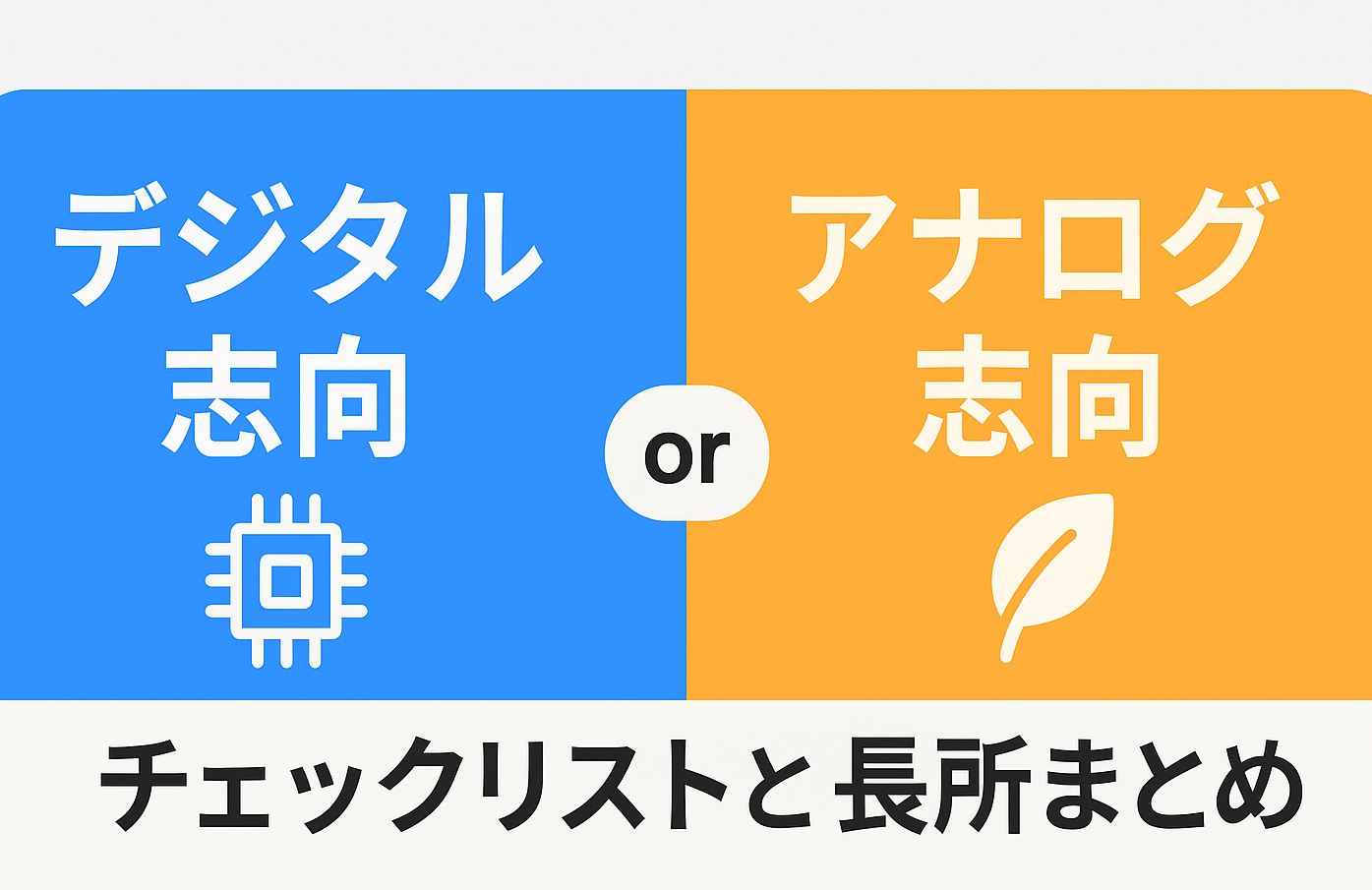前回の記事「あなたの思考はデジタル?アナログ?──自分の脳の“使い方”を知って活かすには」で触れたように、人には脳の使い方の傾向・好みがある。
今回は自分の脳の傾向を知るための簡易チェックリストと、それぞれのタイプの長所を紹介する。
注)このチェックリストは性格診断ではなく、脳の使い方の癖を見る簡易テストである。学術的な診断ではなく、実用的な指標として気軽に楽しんでほしい。
チェックリストの使い方
各項目に「はい/いいえ」で答える。【1】の項目の合計点をD(デジタル志向)スコア、【2】の項目の合計点をA(アナログ志向)スコアとする。
デジタル志向/アナログ志向チェックリスト
【1】(Dスコア/デジタル志向)
- 時系列順に説明されるより、結論を先に話してほしい。
- 音楽を聴くときは、歌詞の意味や音の構成に注目する。
- 旅行は行き当たりばったりより綿密に計画を立てたい方だ。
- 文法の規則が好きだから言語学習は楽しい。
- 家電やパソコンなど身の回りの機械類がどうやって動いているのか興味がある。
- 人間の本質を探ることが好きだ。
- 美術館や博物館では、必ず説明文を読む。
- 効率の良い方法やルーティンを考えるのが得意だ。
- パソコンのデスクトップやスマホのホーム画面は常に整理整頓されている。
- 白黒ハッキリつけたがる性質だ。
【2】(Aスコア/アナログ志向)
- 大勢の人がいる集まりで、自分がどう振る舞うべきかすぐにわかる。
- 自然の豊かさを全身で感じても、具体的に言葉で描写しようとは思わない。
- 人と何気ない雑談や世間話をすることが好きだ。
- 街中で、どちらの方向から来たか分からなくなることは殆どない。
- 馴染みのないスポーツでも、観戦していると大体ルールがわかる。
- カラオケで歌うときや料理をするとき、自分なりのアレンジをしたくなる。
- 人に何かを説明するとき、言葉よりも絵や図を使うことが多い。
- 家具を組み立てるときは、説明文よりもイラストや写真を見る。
- 物事の方法や理由を説明するのが苦手だ。
- 行き先を言葉で説明されるより、地図を見た方がわかりやすい。
判定の方法
- Dスコア>Aスコア:デジタル志向が強い傾向
- Aスコア>Dスコア:アナログ志向が強い傾向
- Dスコア=Aスコア:ハイブリッドタイプ
Dスコアが高ければデジタル志向が強く、Aスコアが高ければアナログ志向が強い。
それぞれのタイプの長所と短所
- デジタル志向が強い人
物事のルールを把握したがる傾向がある。曖昧なことが苦手で白黒はっきり付けたがることが多い。言語化や数値化で目に見える形にすることに快感を覚える。順序立てて考えたり分析したりすることが得意。 - アナログ志向が強い人
物事の全体を見る傾向がある。理屈よりも感覚を重視することが多い。言葉よりも絵や図で示された方が理解しやすいタイプもいる。比較的方向感覚に優れており直感的に把握することが得意。 - ハイブリッドタイプ
両者の傾向をバランスよく持っており、状況によって切り替えることが可能。
それぞれのタイプの活かし方
- デジタル志向が強い人
言語化や分析能力を武器にできる。学習や仕事の場では、ルールを整理したり、手順をマニュアル化したりすると強みが発揮される。ただし「曖昧さ」や「直感的判断」を避けすぎると柔軟性を失うので、ときには「とりあえずやってみる」姿勢も取り入れるとバランスが良い。 - アナログ志向が強い人
直感的に状況を把握したり、人の感情を汲み取ったりすることに強い。創造的な活動や、臨機応変な対応が求められる現場で力を発揮する。ただし理屈を後回しにしすぎると誤解を招くこともあるので、必要に応じて言葉やデータで裏付ける工夫をするとさらに強みが活きる。 - ハイブリッドタイプ
場面に応じて切り替えができるため、幅広い環境に適応しやすい。強みは「通訳者」のように両者を橋渡しできること。チームや人間関係の中では、デジタル派とアナログ派の間をつなぐ役割を担える。
まとめ:自分の強みを活かそう
デジタル志向もアナログ志向も、それぞれが持つ特性に価値がある。どちらが優れているわけでもなく、必要に応じて両方を使い分けられるのが人間の強みだ。
自分の傾向を知ることは、思考のクセを理解し、行動の選択肢を増やすことにつながる。得意な型を武器にし、もう一方を補助として備えておけば、どんな場面でも柔軟に対応できる。