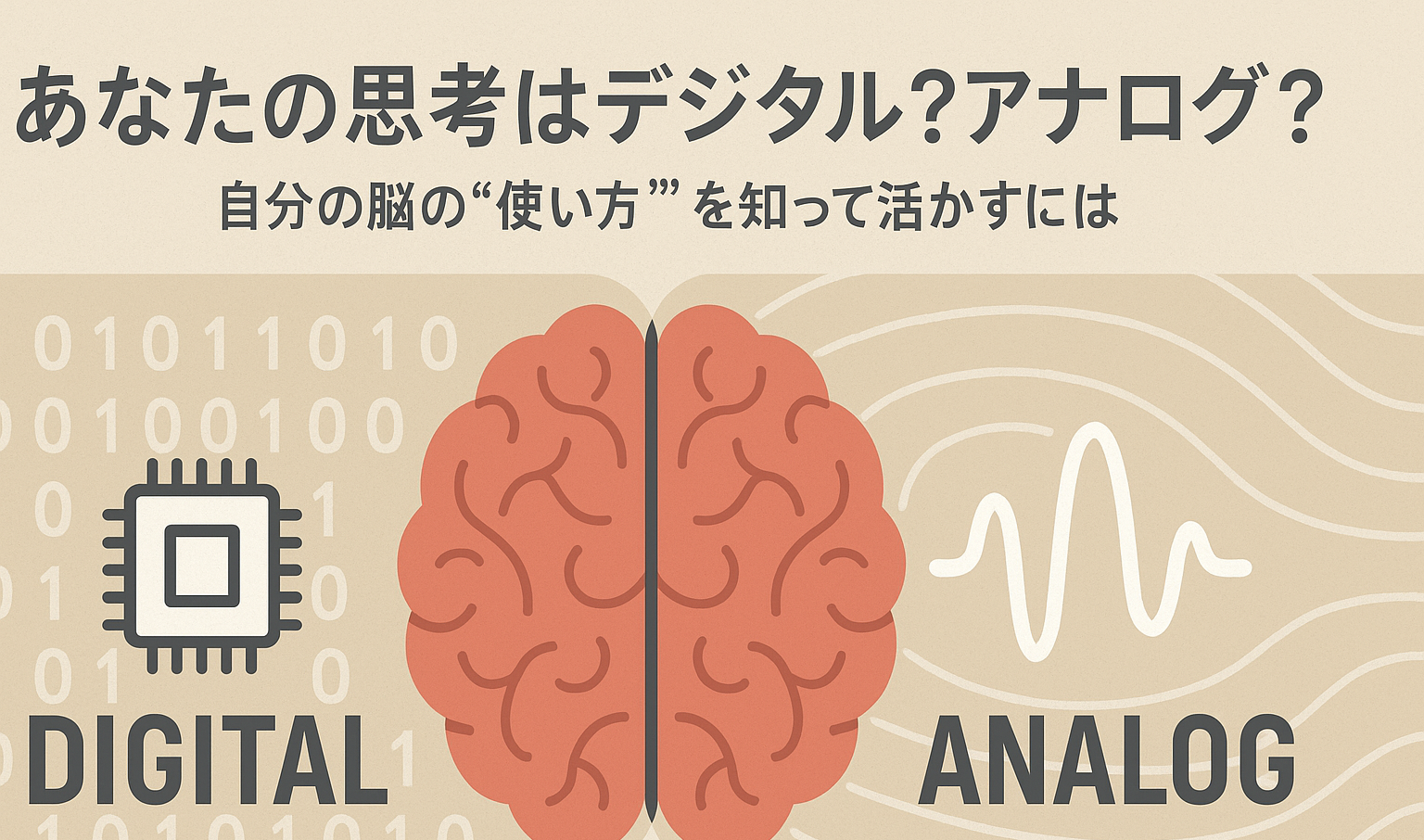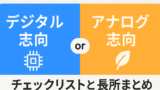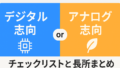「男性脳/女性脳」という言葉を聞いたことがあるだろうか?「自分は共感より理屈を求めるから男性脳だ」と感じている男性は多いと思う。でも実際は、脳の仕組みに性別はあまり関係がない。人によってよく使う思考回路が違うだけだ。今回は、二つの脳の使い方の傾向と、その活かし方について考えてみたい。
ルール作戦と見たまま作戦
前回の記事「子供の学びは“デジタル”じゃない──9歳のレッスンから見えた世界の受け取り方」で触れたとおり、人には脳の使い方において二つの傾向がある。
- ルール作戦:先に言葉でルールを確認してから、応用に向かう。
- 見たまま作戦:お手本を真似して全体像をつかみ、あとから整理する。
ここでは、前者を好む人を「デジタル志向が強い」、後者を好む人を「アナログ志向が強い」と呼ぶことにする。
デジタル志向、アナログ志向とは
この場合のデジタル/アナログとは、コンピュータの話ではない。本来の意味は、「デジタル=離散的」「アナログ=連続的」だ。
・デジタル:枝葉を削ぎ落とし、本質を抽出して捉える(=離散的)
・アナログ:物事を連続的に捉え、感覚として全体を受け入れる(=連続的)
「ルール作戦」で定義から入る態度は、物事を白黒はっきりさせる点で「デジタル」的だ。一方、「見たまま作戦」は、曖昧なままでもまず受け入れてみるという点で「アナログ」的だと言える。
「思考」ではなく「志向」という表現を使っているのは、脳の使い方だけでなく好みや意思も含まれているからである。
- デジタル志向=ルール作戦
先に言葉で意味づけしてから動く態度。定義→実行の順が心地よい。 - アナログ志向=見たまま作戦
物事をありのまま受け入れる態度。体験→あとで名前をつけるのが合う。
どちらが優れているかではない。脳の使い方と好みの違いだ。よく言われる「男性脳/女性脳」や「共感能力/システム化能力」と似た面はあるが、ここでは性別やスキルではなく思考のクセや好みとして扱う。
次に、私の二つの仕事:日本語教師とイベント司会者の視点から、デジタル志向とアナログ志向の具体的な違いについて記述する。
日本語教育での違い
市販の教科書はデジタル志向が強い人に合わせたものが多い。まず、文法のルールを示し、例文、練習という順に進む。教科書で定着しづらい生徒は、アナログ志向が強い可能性がある。その場合は、最初に多くの例文を読ませるのが効果的だ。インプット量を増やした後に説明をすると、すんなり受け入れてもらえることが多い。
ちなみに、私は発音指導を専門にしている。理屈を求めるデジタル志向が強い上級者には、まず「アクセントの型」や「発音のルール」を教える。その後に大量の例文を提示すると効率よく吸収してもらえる。
- デジタル志向の学び方:理屈の説明→例文→実践練習。
- アナログ志向の学び方:例文を先に音読・暗唱→そのまま再現→最後に要点を一言で説明。
イベント司会での違い
もう一つの仕事、イベント司会でも志向の違いを大きく感じる。
私は駆け出しの頃、「自分は司会者に向いてないかも」と感じていた。というのも、あまりにもアドリブが苦手だったからだ。アドリブを自然に挟めるのはアナログ志向が強い司会者の特長だ。場の空気をアナログ的に──あるがままに受け取り、自分を適応させ、感覚的なアウトプットができる天性の才能を羨ましく思っていた。
しかし、今ではどんな状況・ハプニングにも対応できるようになった。それは、脳内にデータベースを作ったからだ。経験した全ての状況を蓄積して、分析し、状況に応じて組み合わせて利用できるようにした。
アナログ志向が強い人の方がアドリブに強いのは事実だが、そうじゃないからと言って諦めることはないということを身をもって体感した。
- デジタル志向のイベント司会者:台本や話し方を構造化し、状況に応じて組み替える。
- アナログ志向のイベント司会者:会場の空気をそのまま受け取り、直感的・感情的に調整する。
自分の特性を知り、強みを活かす戦略
日本語教育でも、イベント現場でも、人にはそれぞれ“やりやすい形”がある。それを意識するかどうかで、パフォーマンスの質が変わってくる。
私は、自分が「デジタル志向」であることを理解してから、明らかに戦い方が変わった。
たとえば今は、「準備は徹底的にデジタル」「本番は意図的にアナログに寄せる」という配合で臨んでいる。直感に頼るのではなく、直感を“演出する”のだ。冷静に、計算された“即興らしさ”である。
そもそも思考の傾向を言語化したくなる時点で、すでにデジタル志向の強さが顔を出しているのかもしれない。
注釈|デジタル志向とアナログ志向は対立するものではない
最後に補足しておきたい。
デジタル志向とアナログ志向は、優劣や二者択一ではない。どちらも人間の中に存在しており、場面によって切り替わるものだ。強いて言えば、咄嗟の判断でどちらに寄るか──という“利き手”のような感覚に近い。
私自身は、得意な方(=利き手)を活かしながら、もう一方の使い方も学び、使い分けられる準備をしておくのが良いと思っている。
用語メモ:デジタル志向/アナログ志向
- デジタル志向:言語化・数値化によって、世界を切り分け、白黒はっきりさせようとする傾向。分類・構造化が好きな人。
- アナログ志向:言語にしきれない感覚や曖昧さをそのまま受け入れる傾向。雰囲気や直感、余白を大事にする人。
1行自己紹介
鈴木笑里(すずきえみり)/イベント司会者&日本語教師。いろいろなものに名前を付けるのが好き。
※次回は、「デジタル志向/アナログ志向」それぞれのチェックリストを公開予定。自分の“思考のクセ”を見える化したい人はぜひ読んでみてほしい。
Next:デジタル志向とアナログ志向を見分けるためのチェックリストとそれぞれの長所まとめ